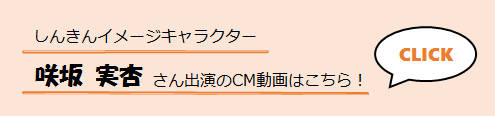住宅ローンの金利はどうやって決まるのでしょうか?
高度なシステムで管理され、何かの要因で変動するのか?それともルールなど存在しないのか?
住宅ローン金利の決まり方やその決定プロセス、金利変動の仕組みについてわかりやすく説明します。基礎知識的な部分から説明しますので、住宅ローンの金利について知りたい人はぜひ参考にしてください。
目次
住宅ローンの金利とは?もう一度基本を確認しておきましょう
住宅ローンの金利は次の計算式で算出されます。
【基準金利-優遇幅=適用金利】
この計算式について詳しく見ていきましょう。
基準金利とは?
基準金利は、金融機関が独自に設定する金利で、住宅ローン金利の「定価」にあたります。店頭金利とも呼ばれます。
優遇幅とは?
優遇幅とは、基準金利から引き下げられる「利率の幅」のことで「割引」と考えるとよいでしょう。
優遇幅には、当初期間優遇タイプと全期間優遇タイプの2種類があります。
当初期間優遇タイプとは、住宅ローンの借入当初は優遇幅が大きく、一定期間経過後は優遇幅が小さくなるタイプです。当初引き下げプランとも呼ばれ、多くの場合、固定金利選択型で適用されます。
全期間優遇タイプと比較すると当初の優遇幅は大きく設定されていることが多いため、初期の返済負担を抑えたい人に向いています。ただし、一定期間を経過すると優遇幅が縮小し、ケースによっては優遇が適用されなくなることもあります。
全期間優遇タイプとは、返済を始めてから完済するまで金利優遇幅が一定に保たれるタイプのことです。一般的には当初期間優遇タイプと比較すると、優遇幅は小さく設定されていますが長期的な返済となる住宅ローンでは借入額が同額のケースでの総返済額を比べると、全期間優遇タイプのほうが総返済額を抑えられることもあります。
ローン契約前にどちらが得であるかを見極めることは困難です。当初期間終了時点の適用金利が分からなければ、それぞれの総返済額の比較ができないからです。
返済期間中の繰り上げ返済を計画的に実行できるのであれば、返済初期の利率が低く設定されている当初期間優遇の方がおすすめと言えるでしょう。
また、優遇幅の適用条件は金融機関により異なります。ローンを申し込む前に、自分がクリアできる条件があるか確認する必要があります。主な条件として次のようなものがあります。
・公共料金の口座引き落としや給与振込口座をローン申込み金融機関の口座に変更する
・ローン申込み金融機関が発行するクレジットカードを所有している、または作成する
・キャンペーン期間中にローンを申込む
・投資信託口座を開設する
・申込みから契約までの手続きをオンラインで行う
適用金利とは?
適用金利とは、実際に住宅ローンを借りるときの利率であり、基準金利から優遇幅を差し引いた金利です。
一般的に金融機関の融資では、借り手の返済能力に応じて適用金利を決めます。
固定金利と変動金利とは?

住宅ローンの金利タイプは大きく「固定」と「変動」の2つに分けられます。それぞれの特徴と仕組みを確認していきましょう。
固定金利とは?
固定金利とは、決められた期間(一定期間または完済までの期間)は金利が変わらない金利タイプです。
一般的に住宅ローン固定金利は「長期プライムレート」と呼ばれる、金融機関が最優良企業に対して、1年以上の長期貸出をする際の最優遇金利を参考に決定します。
長期プライムレートは、長期金利といわれる10年もの国債金利の影響を受けるため、固定金利で住宅ローンを借りようと考えている人は、10年もの国債金利の動向と毎月の固定金利の傾向をチェックするとよいでしょう。
変動金利とは?
変動金利とは、借入期間中に適用金利が変動する金利タイプです。
信用金庫や銀行などの金融機関は短期プライムレート等を参考に決定しています。
短期プライムレートとは、金融機関が、最優良企業に対して、1年未満の短期貸出をする際の最優遇金利のことで、経済情勢等によって変わる金利と言えます。世の中の金利が急騰した時などは、利率が大幅に引き上げられる可能性があります。
変動金利の場合、多くの金融機関では、急激に金利が上昇した際に毎月の返済額が急に上がらないための施策として、返済額5年間固定ルールと返済額125%・1.25倍ルールが適用されることがあります。
返済額5年間固定ルール
変動金利を選択した場合、一般的に半年に1回基準金利の見直しがありますが、万が一適用金利が上昇したとしても5年間は毎月の返済額は変わらないというルールです。
ただし返済額は変わりませんが、適用金利が変わると返済額に占める元金と利息の割合は変わる可能性があります。
返済額125%・1.25倍ルール
金利上昇後の返済期間の5年が経過し6年目に返済額が増額になるとき、新しい返済額は直近5年間の返済額の125%以内とするルールです。例えば従前の毎月返済額が1万円であれば、見直し後の上限返済額は1万2,500円になります。
5年ルールと返済額125%・1.25倍ルールを適用すれば、金利が上昇しても返済額は急には増えません。
ただし実際は利息支払いが免除されるわけではなく、支払いが先送りされ住宅ローン契約の終盤にしわ寄せされます。
返済額5年間固定ルールや返済額125%・1.25倍ルールは全ての金融機関で採用されているわけではなく、一部のネット銀行等では採用していません。
住宅ローン金利の基本法則
住宅ローン金利は、毎月の返済額や総返済額を大きく左右する重要な要素です。その決定には、経済情勢や金融機関の運用方針が深く関わっています。金利の動向を理解することで、より適切なローンタイプを選択できるようになります。
【固定金利】住宅ローン固定金利は国債利回りの影響を受ける
固定金利に影響を与える主な要因として、長期金利といわれる10年もの国債金利があります。固定金利で住宅ローンを借りようと考えている人は、10年もの国債金利の動向と毎月の固定金利の傾向をチェックするとよいでしょう。
【変動金利】日銀が決めている政策金利の影響を受ける
変動金利は短期プライムレートを基準としています。
短期プライムレートは、日銀が決めている政策金利や経済情勢等によって変わるため、世の中の金利が急騰した時などは、住宅ローン金利も引き上げられる可能性が高くなります。
住宅ローン金利はどうやって決まるのか?
各金融機関は基準金利に対して独自の優遇幅を設定し、適用金利を決定しています。
固定金利が決まるプロセス
住宅ローンの固定金利は、国債市場で取引される10年国債の利回りの影響を受けます。短期金利は日本銀行の金融政策等によって決まりますが、長期金利は主に、物価の変動や短期金利の推移(金融政策)等の長期的な予想で変動します。
よって、景気が悪くなれば低くなり、景気が良くなれば高くなるという傾向にあります。
変動金利の決定プロセス
基準金利をもとにした年2回の見直しで基準金利が上下動しなければ、変動金利も変動しません。
住宅ローン金利は、過去に8.5%まで上昇した時期もありましたが、1999年以降は日銀のゼロ金利政策により低金利が続いています。将来の動向は金融政策次第で変わるため、十分な注意が必要です。
参照:一般社団法人住宅金融普及協会「過去の住宅ローン金利の推移」
まとめ
住宅ローン金利の上昇に備えるためには、繰上返済や固定金利への変更、他の金融機関への借り換えなどがあります。多くの場合、現在借り入れ中の金融機関で金利プランの変更はできますが、借り換えはできません。
住宅ローンを組む予定の人や現在借入中の人は信用金庫や銀行などの金融機関に相談することをおすすめします。きっと親身になって相談にのってくれるはずです。